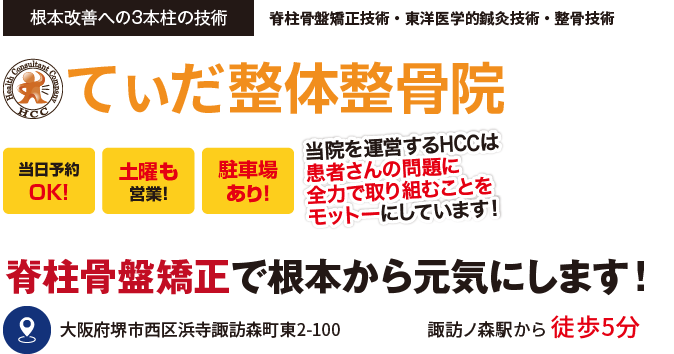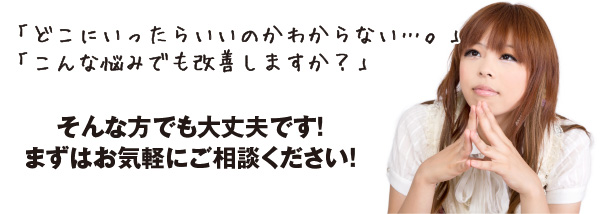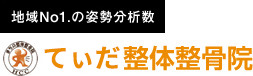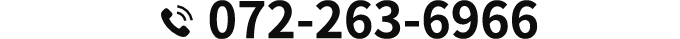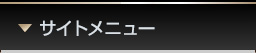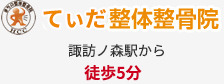不眠症について
2020.10.31
夜なかなか眠れない、夜中に何度も目を覚ましてしまうなど、不眠症にも様々な症状があります。
不眠症は4つのタイプに分けられます。
①寝つきの悪い「入眠障害」
②眠りが浅く途中で何度も目が覚める「中途覚醒」
③早朝に目が覚めてしまう「早朝覚醒」
④眠ってもぐっすり眠れたという満足感が得られない「塾眠障害」
1.入眠障害
床にはいってもなかなか寝つけない、眠りにつくのに30分~1時間以上かかり、それを苦痛と感じる状態です。不眠症の訴えで最も多く、不安や緊張が強いときに起こりやすいと言われています。入眠障害の原因は、生活習慣、ストレスなどの心理的要因が主な原因で、身体的な疾患が絡んでいる場合もあります。現代人は仕事の頑張りすぎなどが原因となって、睡眠モードにうまく入ることができずに、なかなか寝つけないという方も多いようです。
2.中途覚醒
睡眠中に何度も目が覚めて、そのあと、なかなか寝つけない状態です。年をとるにしたがって、眠りがだんだんと浅くなり、目覚めやすくなります。日本人の成人の不眠で最も多く、中高年・高齢者に多くみられると言われています。寝汗や不安、交感神経の昂りなど、様々な原因によって病的な中途覚醒となってしまうこともあります。
3.早朝覚醒
自分の望む起床時刻より2時間以上早く目覚めてしまう状態です。年をとると体内時計のリズムが前にずれやすく、また若い人に比べて夜遅くまで起きているのが辛くなるので、早寝早起きになります。高齢者によく見られます。また、うつ病にもよくみられる症状です。
4.熟眠障害
睡眠時間は十分なのに、ぐっすり眠った感じが得られない、眠りが浅い状態です。睡眠時無呼吸症候群や寝ている間に足がぴくんぴくんと動く周期性四肢運動障害など、睡眠中に症状の現れる病気が関係していることもあります。睡眠時間には個人差があり、日本人の平均睡眠時間は7時間程度としているものの、3時間程度でも翌朝すっきりしている方もいれば、10時間程度眠ってすっきりするという方もいます。
不眠症と診断されるのは、上記のような症状が週に2回以上みられ、かつ少なくとも1か月間は持続した場合となります。また、眠れないことによって苦痛を感じているか、社会生活または職業的機能が妨げられているかも診断のポイントとなります。
自分でできる不眠の対策方法は主に2つです。
①不眠の原因として思い当たることを取り除くことです。仕事や人間関係などの悩みがある場合、その悩みを改善すれば不眠の改善につながる可能性が充分にあります。
②生活習慣の見直しです。まずは、睡眠環境を整えていきましょう。好きな音楽を聴いたり、読書をしたりと、自分の好きなことでリラックスする時間をとり、副交感神経を活発にさせることが大切です。ぬるめのお風呂も有効です。しかし、お酒は睡眠が浅くなり、中途覚醒に繋がることもありますので、寝る前のお酒は控えましょう。
東洋医学でも不眠のツボというものが存在します。それだけでなく、何が原因として不安を与えているかを見極めることがポイントです。どんな些細なことでもご相談いただけることが解決への糸口となるかもしれませんね。
むくみについて
2020.10.14
このようなことでお悩みありませんか?
〇寝起きで顔がむくんでいる
〇夕方になると靴がきつい
〇デスクワーク、立ち仕事をしている
〇夜中にトイレに行く
全てむくみの原因や、むくみによって引き起こされることの一つです。
むくみとは?
身体を作っている体液が余分に余った状態です。手や足だけでなく、顔や内臓などのどの部分にもみられる可能性があります。毛細血管から漏れ出した体液が再吸収されずに、細胞や組織の隙間にあふれて溜まってしまった状態です。リンパ管による吸収のバランスが取れていない事でも起こります。
むくみの種類
〇生理的なむくみ
座りっぱなしや立ちっぱなしなど、長時間同じ姿勢を取ったりすることで起こります。体の動きが少ない為に、余分な体液を運ぶ「筋肉のポンプ作用」が働かなくなり、足がむくんだりします。また、女性ホルモンの影響や、カリウムやマグネシウム不足、運動不足などで生じます。
〇全身的なむくみ(病的)
心臓や肝臓、腎臓の病気で引き起こされることがあります。血管障害や代謝不全が原因になるので、その場合は注意が必要です。
リンパ管に流れるリンパ液が原因でおこるむくみもあります。原因としては、がんの術後に起こることが多くあります。がんの手術ではリンパ節を切除したり、放射線治療によりリンパ節を損傷することがあるため、手足のリンパ液の流れが悪くなり、むくみが生じます。
また、静脈瘤も多くみられる原因の一つです。足の静脈には、一度心臓に向かった血液が逆流しないように弁がついています。その静脈便が何らかの原因で壊れてしまい、逆流した血液がたまってしまうことで生じます。
エコノミークラス症候群もむくみの原因の一つです。長時間のバス移動や飛行機、病気での寝たきりなど、同じ姿勢を取り続けた後に足の静脈に血栓ができることがあります。足の静脈に血栓ができると、静脈血が心臓に戻りにくくなりますので、足のむくみが生じやすくなります。また、その同じ姿勢から動き出した時に、血栓が肺や脳に移動し、血管を詰まらせてしまうこともありますので注意が必要です。
むくみ対策
むくみを解消し予防するためには、むくみやすい生活を改善することが必要です。
マッサージやストレッチで筋肉を柔軟に保つことで、「筋肉のポンプ作用」を働かせることで、リンパ液や血流を改善し、手足に溜まった余分な体液を心臓に戻すことが出来ます。
食事でも予防することが出来ます。水分や塩分の量を控えめにすることです。体の中の過度な塩分を排出してくれるカリウムを多く含む食材(バナナ、ホウレンソウ、納豆など)を摂取したり、血流をよくする働きがあるビタミンEを多く含む食材(アーモンド、モロヘイヤ、いわしなど)を摂取することで予防することが出来ます。
同じ姿勢を長時間取らないことも大切な予防の一つです。運動不足の改善です。また、体を冷やさないようにすることも重要です。
しびれについて
2020.10.14
一言で「しびれ」といっても、手指や足、首、背中、肩、顔、腰など、体のあらゆる部分に生じます。しびれも治療が必要なものとそうでないものがあります。長時間の正座などで足がしびれるようなものは心配ありませんが、脳梗塞や高血圧などの内科疾患、頸椎、脊椎、腰椎などの病気が引き金となってしびれが生じている場合は治療が必要となってきます。
「我慢すれば大丈夫」「暖かくなれば治る」などと簡単に考えていては危険な場合もありますので、注意が必要です。
足のしびれ
足のしびれは、神経性と血管性に大きく分けられます。神経性の場合は、椎間板ヘルニアや脊椎、筋肉が関与している場合が多くあります。血管性の場合は、血管障害により血流が悪くなり、痛みやしびれが生じます。
足首やつま先がしびれる場合は「足根管症候群」が考えられます。ふくらはぎからくるぶしを通る神経が圧迫を受け、炎症を起こし、痛みやしびれになります。
腰から足にかけてしびれる場合は「椎間板ヘルニア」や「梨状筋症候群」などが考えられます。軟骨の変性や強い筋緊張により、神経が圧迫を受け、炎症を起こし、痛みやしびれになります。
どちらも圧迫や牽引を改善し、神経血流を改善することで症状が緩和されることがあります。
手指のしびれ
手や指のしびれは脳に原因があってしびれることが考えられますので、要注意部分だとも言えます。
特に圧迫されやすいのは、頸椎、鎖骨、肘、手首の4か所があります。
頸椎では、頚部椎間板ヘルニアや頸椎の変性などが考えられます。鎖骨は、鎖骨の下を神経の束が通っています。その束が鎖骨と周囲の筋肉の状態により、圧迫を受けることで痛みやしびれが生じます。「胸郭出口症候群」と呼ばれています。肘は、「肘部管症候群」と呼ばれ、筋肉の萎縮や筋力低下なども見られます。手首は「手根管症候群」と呼ばれ、女性ホルモンのバランスが変化したときに靭帯の肥厚や変性で神経が圧迫を受け、痛みやしびれとともに手指部の筋肉萎縮や筋力低下も見られることがあります。
内科疾患で起こるしびれ
血管障害の一つの原因として、糖尿病があげられます。合併症の一つとして、末梢神経障害があります。手足のしびれやこむら返り、走るような痛みがあれば要注意です。足の裏に1枚紙を貼ったような感覚、鈍感になるような場合も注意が必要です。足が冷たく感じたり、足が細くなったりする場合は、足の動脈が詰まっている場合が考えられます。
様々な原因が考えられますので、些細な症状でも我慢せずに、ぜひお気軽にご相談ください。
頭痛について
2020.05.30
頭痛はよく見られる症状のうちのひとつですが、その原因は様々です。
頭痛を大きく分けると
第一次性頭痛
〇片頭痛
〇緊張型頭痛
〇群発頭痛およびその他の三叉神経・自律神経頭痛
〇その他の一次性頭痛
第二次性頭痛
〇頭頚部外傷
〇頭頚部血管障害
〇非血管性頭蓋内疾患
〇物質またはその離脱
〇感染症
〇ホメオスターシスの障害
〇頭蓋骨、頚、眼、耳、鼻、副鼻腔、歯、口あるいはその他の顔面・頭蓋の構成組織の障害に起因
〇精神疾患
等があげられます。
筋緊張からくる頭痛、血行不良など原因は様々ですが、今回は東洋医学的な側面から頭痛を見ていきましょう。
経絡で考える頭痛
東洋医学的にはいくつかのアプローチがあります。鍼灸の特徴である、経絡から頭痛を考えていきましょう。頭痛が出ている場所で分類する事が出来ます。
〇前頭部(陽明頭痛)
大腸経、胃経の変動としてとらえます。消化器との関連が深いので、みぞおちの痛みや消化不良、ゲップ、膨満感、嘔吐、便秘などの症状を伴うことがあります。
〇側頭部(少陽頭痛)
三焦経、胆経の変動としてとらえます。耳の症状も含みます。胆経の変動は、おどおどしたり、ため息をつくようになったり、判断が鈍ったりします。また、口苦・両脇のつっぱり、めまい、不眠となることもあります。
〇後頭部(太陽頭痛)
小腸経、膀胱経の変動としてとらえます。小腸の変動は耳鳴り、目や歯の痛みが出ることがあります。膀胱の変動は小便が出にくい、口渇、多飲などの水分代謝の影響もありますが、鼻水や鼻血、腰部、臀部、ふくらはぎの痛みなどの症状を伴うことがあります。
〇頭頂部(厥陰頭痛)
心包経、厥陰肝経の変動としてとらえます。肝の変動は、目が赤くはれたり、涙目、物が見えにくいなどの眼科疾患を伴うことがあります。ストレスやイライラ、怒りや抑うつなども肝に影響を与えます。頭がブヨブヨをむくんだような場合には、刺鍼により頭がスッキリし、目の疲れも取れ、リラックスすることが出来ます。
体の体質に合わせて、施術することが大切です。頭が痛いから肩や首だけに原因があるわけではなく、体の中からアプローチすることで症状の改善に繋がることがあります。
そのためにも、問診や検査などを行うことで原因を絞り、姿勢の歪みなどを分析することで痛みの原因を見つけ出すことが大切です。
どんな些細なことでもスタッフにお伝え頂くことが必要です。患者様の治療への積極的な参加が必要です。
すぐに痛み止めに頼らず、お気軽にご相談ください!
体温について
2020.05.16
体温とは、文字通り体の温度でありますが、平熱とはどのようなものでしょうか?
自分の平熱を知ることから始める
まずは、自分の平熱を知りましょう。平熱を知らないのに、37度を超えたとたんに「熱が出た」という方がおられます。平熱が37度の場合は、熱を測って37度でも発熱とはいいませんよね。
体温は、外気温や女性の場合は性周期などの様々な影響を受けて変化するものです。変化するものは、定期的に観測することが望ましいです。血圧でも同様ですが、朝起きた時、午前中、午後、夜の4回計測してみましょう。より正確に自分の体温を知ることが出来るでしょう。
1日のうちでも朝起きた時が最も低く、夕方が最も高いという事が調査からわかっています。食事の後や運動後、お風呂の後なども体温が上がりやすいので注意が必要です。
日本人の平均は、平熱が36.6度~37.2度の間と言われています。低体温症の方などは、これらよりも約1度低い方たちということになります。
低体温になるとどうなるのか?
極度なダイエット、ストレスや老化が原因で、熱の産生と放散のバランスが崩れたことによるものを言います。そのまま放っておくと、様々な病気を発症し、突然死の原因にもなりかねません。低体温症になるとどうなるのか。
血行不良、血圧上昇、消化不良、食欲不振、代謝の低下、体力の低下、意欲・集中力の低下、免疫力の低下など
このような症状が出てくることがあります。
正しい体温の測り方
みなさんは、体温計をどのように使って体温を測っているでしょうか?体温計の先の部分をわきに軽く挟んだだけで測定していませんか?
正しいはかり方は、
①体温計の先の部分を、斜め下から差し込んでわきの中心に当てる。(約30度くらいの傾き)
②しっかりとわきを締める。よりわきを締める為に手のひらを上に向けましょう。
③安静にする。
わきの中心に当てることが出来ると、より正確な体温を測ることが出来ます。離れていたり、角度が大きいと、実際より低く計測される場合があります。
体温を上げるポイント
低体温症になると体調を崩すことがお分かりになったと思います。では、実際に体温を上げるにはどのようなポイントに注意するべきか。食事や運動、鍼灸治療などで体温を上げることが出来ます。
食事は、根菜類を中心に取るように心がけることがポイントです。有名なのはショウガです。土の中で育つ野菜は、冬に旬を迎えるものが多く、ゆっくりと育ちます。太陽の力を十分にためた野菜だと言えます。しかし、ダイコンやゴボウは逆に体を冷やすとも言われます。生で食べると体を冷やすと言われていますので、調理法を工夫して頂くことで、体を健康に保つことが出来ます。
体温のはなし
2020.05.16
病院でのバイタルチェックなど、体調のバロメーターとしても知られている体温ですが、実は正しく知らない方も多いのではないでしょうか?
人の体温は変わらないの?
気温が暑くなれば手足や顔が赤くなり、汗をかきます。また、寒くなれば手足が冷たくなったり、ふるえたりします。
体が赤くなることで毛細血管が広がり、体内の熱を逃がしやすい状態になり、汗をかくことで体温を調節しています。また、寒くなると血管が縮むことで冷たくなり、体をふるわすことで筋肉を伸縮させ、体温を上げるように調節しています。
私たちの体は、こうして体温を一定に保つようにいつもコントロールしているのです。
体温を測る場所はどこがいいの?
体温は体の中心に近づくほど安定しています。体の末端や表面の温度は、季節や環境温の影響を強く受けます。一方、体の中心部に近いところの温度は、脳や心臓など大切な臓器の働きを保つために高く安定しています。この安定した体温を測ることが出来ればいいのですが、体の内部の温度なので日常的には測れません。
体に負担をかけずに簡単に検温できる場所として、わき、口、耳、直腸などの体の行面に近い場所が用いられています。測定する場所ごとに、必要な時間や方法が異なるため、得られる温度も異なります。平熱も部位により違う為、それぞれの平熱を知る必要があります。
場所ごとの測定にかかる時間
耳・・・約1秒
口・・・約5分
わき・・・約10分
直腸・・・約5分
平熱と発熱
人によって平熱は違うことがあります。日本人の7割くらいは体温が36.6℃から37.2℃の間と言われています。37℃で発熱と言われる方も多いかと思いますが、実は平熱であることがおおいと言われています。
しかし、平熱が低い人は、37℃でも発熱を疑うこともあります。感染症法では、37.5℃以上を「発熱」、38℃以上を「高熱」と分類しています。
体温のリズムとは?
平熱をはかるタイミングでも体温がかわるので、平熱は一つではありません。病気でなくても、運動していなくても、体温は上がったり下がったりします。
早朝は低く、夕方には高くなるリズムがあります。これを「概日リズム」といいます。1日の差はほぼ1℃以内が正常といわれています。
ですので、時間帯を決めての検温が大事にあっていきます。1日1回の検温で平熱と考えるのは適切ではありません。上記にあるように、1日の中でも体温は変動があります。
起床時、昼食前、夕方、就寝前というように、時間を決めて測ることが望ましいです。高齢者の場合は気温による影響を受けやすいので、季節による違いも平均をとっておくといいでしょう。
肩背部の痛みについて
2020.04.18
こんにちは!肩や背中の痛みについてお悩みの方が多くおられる中で、筋肉や神経、姿勢に原因のないものも存在します。今回は「胆石」についてお話しさせていただきます。
胆石とは?
胆石は、非常に軽いものでコレステロールやビリルビンがもとになって出来上がることが多くあります。胆石ができやすい人として、
①女性 ②肥満 ③加齢 ④洋風の食事が多い ⑤家族に胆石になった人がいる など
一般的には30代~50代の肥満気味の女性に多いとされています。
また、胆石がある場所によって、3種類の名前がついています。
①胆嚢結石
胆嚢は、肝臓でできた胆汁を濃縮する場所で、一定の時間とどまっているために最も多くできやすいと言われています。
②総胆管結石
胆嚢でできた結石が何らかの拍子に胆管内に転げ落ち、詰まってしまうことで起こることもあります。胆管結石が起こると、胆汁の流れが滞ってしまうことから、黄疸が生じたり、胆管が結石を押し出そうと動くことから激しい痛みが生じたりすることがあります。
③肝内胆管結石
まれにですが、肝臓内にある胆管に結石ができることがあります。
胆石と肩背部の痛み
胆石があるからと言って全員に症状が出るわけではなく、無症状の方も多いと言われています。しかし、胆石が移動することで狭い通路に詰まってしまうと「胆石発作」を起こしてしまい、痛みという症状となって現れてきます。
腹痛や疝痛(せんつう)と呼ばれる強い痛み、右側のみぞおちや右下腹部、右の背中が痛むことも多く、胃も痛みと間違う人が多いと言われています。
胆石発作は食後や夜間に起こることが多く、数十分から数時間にわたって続いてそのうちに落ち着くと言われています。また、脂っこい食事をとった後や食べ過ぎた後は注意が必要で、発作を起こすことがあります。吐き気や嘔吐、炎症が加わると発熱もみられ、黄疸や肝障害を併発することもあります。
肩や背中、わき腹の痛みを感じた時、何か動かしたから痛みが出たのかな?と軽く考えることは危険かもしれません。
胆石の痛みを和らげるツボのご紹介
症状が軽いものや慢性化したものにツボ療法を行ってみてください。
一番下の肋骨の先端にあるツボが京門(けいもん)になります。軽く押してみて強い痛みを感じる場合は胆石の可能性があります。両手を腰に当て、親指の腹で左右同時に少し強めに指圧します。また、足にある梁丘(りょうきゅう)や陽陵泉(ようりょうせん)も効果的です。