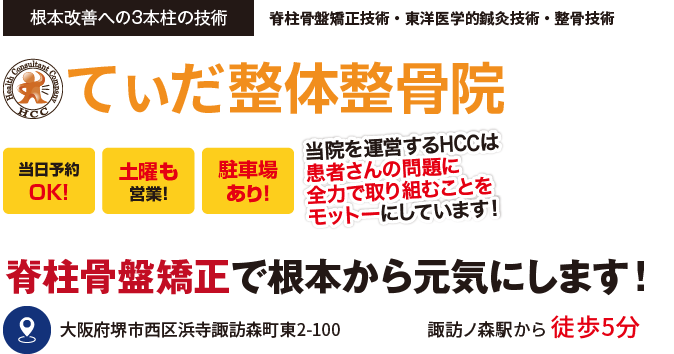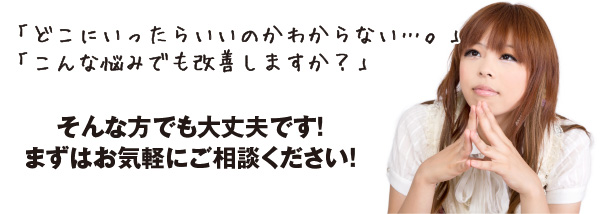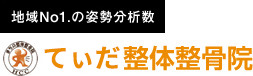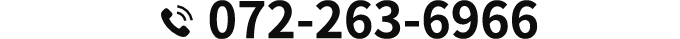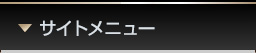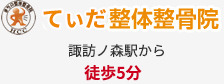マッサージはどんな効果があるの?
2024.07.25
マッサージにはどんな効果があるの?
身体に対して外からの力が加わるため、押さえられている筋肉が一時的に伸びます、
そのことにより硬くなった筋肉をストレッチすることができます。またその筋肉の周りにある血管、
毛細血管、リンパ管も刺激することになるので管の中の流れが良くなり筋肉の疲労回復に役立ちます。
また皮膚や筋肉を刺激するため脳にも刺激が行きリラックス効果を得られている場合は
心拍数が低い時は上昇し高い時は下り正常な状態に戻してくれます。
リンパ管の流れも良くなるのでデトックス効果があり、むくみの改善、ダイエット効果、
身体の免疫力強化にもつながります。皮膚の温度が上がり代謝も良くなり、
皮脂分泌も促進されるので皮膚に潤いがでます。
マッサージが禁忌となる疾患
①急性症 急性熱性病、急性伝染病
②悪性腫瘍 癌、肉腫
③急性炎症 腹膜炎、虫垂炎
④急性中毒 蛇毒、昆虫毒
⑤出血性疾患 吐血、喀血(かっけつ)、脳出血直後
⑥外傷創傷部、骨折、脱臼直後
⑦重症の内臓疾患 心臓弁膜症、腎炎
⑧血管病 動脈瘤、高度動脈硬化症
はしないでください。
マッサージは週何回ぐらいやったらよい?
週1回は必要と言われていますが、その人の仕事量、疲労度、ストレス度で身体のダメージは
変わりますので一概に言えません。
施術を施された方がその方の今の身体の状態を1番把握されていると思いますから、
直接聞くのが良いと思います。あとレコーディングと言ってマッサージを受けた時は
身体が軽くなって爽快な気分でやる気が出てくるでしょうが、その身体が軽い状態が
いつまで続いたのか?いつからまたしんどくなってくたのか?
毎日、毎日記録をとっていると良いでしょう。
身体がまた重く感じた時が次に行くべき時だと思います。
そしてその期間がどんどん長くなってきたら、マッサージの効果がすこしづつ現れてきて
健康な生活を取り戻して行く事になっていると思います。
マッサージするとなぜしんどくなるのか?
これまでそこにとどまっていた老廃物や毒素がマッサージを受けることによって
一時的に体中を巡るため各器官が対応できず身体がしんどくなる時があります。
マッサージをするとなぜ眠くなるのか?
筋肉のコリも改善され身体全体が弛緩し、血液やリンパの流れもよくなりデトックス効果も
現れて同時に副交感神経が刺激されるので心身のリラックス効果がもたらされることから
緊張感がなくなり眠たくなります。疲れが溜まっている人ほど無理していた身体が一気に
休めになるので眠たくなります。
骨盤矯正とは?
2024.07.18
骨盤矯正とは?
身体の中心となる骨盤と脊柱
人のからだの軸となる物、形作っている物が骨でありここから人体が構成されていく。
下からいくと足の骨があり、足の骨の上に骨盤がある、その土台となる骨盤の上に脊柱が伸びており、家で言えば大黒柱であり、身長のほぼ半分くらいあり、その上に頭、頭蓋骨が乗っている、脊柱は場所によって呼ばれ方が異なり下から腰椎、胸椎、頚椎と呼ばれる、胸椎の上の方から左右に腕の骨が伸びており、腕の付け根あたりに腕を支えている肩甲骨があり、胸椎の側面からは呼吸をするための肋骨が円筒形状に伸びている。土台が骨盤であり大黒柱が脊柱であります。
骨と筋肉と靭帯の関係
骨が身体のまさに骨組みであるならば、筋肉はひとつひとつの骨を動かす役割や骨と一緒の身体の臓器を支えている。靭帯は骨と骨、筋肉と骨をつないでいる。

骨盤の前後の歪み
骨盤から上にある腰椎との関係が深く腰椎が反っていると骨盤を前に傾き、逆に腰椎がまるまっていると骨盤も後ろに傾向いてしまう。あと骨盤を支えている筋肉が影響を与えており、腰椎を反らす体幹伸筋群、腰椎を丸める体幹屈筋群、また骨盤の下にある足の骨(大腿骨)と骨盤をつないでいる股関節伸筋群が収縮すると大腿骨を後ろに反らす事になるので骨盤は前に傾き、股関節屈筋群が収縮もしくは縮むと大腿骨は屈曲する事になるので骨盤は後ろの傾きます。この4つの筋肉群のバランスで骨盤の前後の傾きがきまります。
骨盤の左右の歪み
骨盤から脊柱に向かって体幹を支えている筋肉はたくさんあり左右に側屈するための筋肉と関係しておりバランスが崩れると左右に傾いてしまう。また脊柱自身がなんらかの原因で曲がってしまう側湾症がある
骨盤の仙腸関節の歪み
骨盤は仙椎5個の結合体である『仙骨』と『寛骨』と呼ばれる腸骨、坐骨、恥骨の結合体を言います。仙骨と寛骨をつなぐ関節を仙腸関節と呼び靭帯に覆われており動くことのない関節ですが女性が出産する時には動きますし、直接的、間接的に骨盤が衝撃を受けて動くこともあります。触診で骨盤の左右の上下差を確認することができ、仙腸関節の歪みによる左右の足の位置の変化も起こります
骨盤、脊柱のねじれ
骨盤、脊柱に前後左右に歪みが一方方向に向かうとねじれます。横向きに寝てもらった時にきれいに横向きの姿勢ができず背中や腰が横向きだけど前に傾いている。傾いている方向とは反対の向きに動かしにくくなっている。
骨盤や脊柱(背骨)に歪みがあるとどういうデメリットがあるか?
①身体が歪んでいると言うことは本来簡単にできる動作がしにくくなり力を入れて動かすことになりエネルギーを消耗しやすい、疲れやすい。
②身体が動かしにくくなることで心理的、精神的に疲れる。考え方まで変わってくる。行動も変わってくる。
③身体の内部の動きも悪くなり血流や代謝が落ちて病気になりやすかったり太ったり逆に痩せてしまう
④動かしにくいところを、無理に動かそうとした時に他の身体の部位に代償動作がおこり補うため、今度はその部位に負担がかかる事になる。
⑤無理をし続けたり、ほおっておく事で他の場所にまで歪みを生じる。身体全体が硬化する。
治療としての骨盤矯正
仙腸関節の歪みや足の長さの変化を矯正するためにカイロベットを使用する。仙腸関節の歪み足の長さが改善される。
腰椎、胸椎の関節の動きが悪くなっている場所をカイロベットで矯正する。骨盤、脊柱の歪みが改善される。
骨盤周りの4つの筋肉群(体幹伸筋群、体幹屈筋群、股関節伸筋群、股関節屈筋群)のバランスを整える。骨盤の前後の歪みが改善される。
骨盤から腰椎に向かって体幹を支えている筋肉や左右側屈に動かす筋肉のバランスを整える。骨盤の左右の歪みが改善される。
硬くなって動きの悪くなっている関節を正常可動域に戻すためストレッチをする。筋肉と関節が伸び骨盤、脊柱の歪みが改善される。

整骨院で交通事故の治療が出来る‼️
2024.07.10
堺市のみなさん、こんにちは!
てぃだ整体整骨院です。
突然ですがみなさんは交通事故の治療を整骨院で受けられることはご存知ですか?
交通事故により怪我をした際に、まずは整形外科など医師が在籍している医療機関での診察をしてもらった後、医師や保健会社の承諾があれば整骨院での治療を行うことが可能になります!
交通事故が起こった時に多いケガはむち打ちです!
当院でも交通事故でむち打ちになられた患者様が来られることが多いです。

むち打ちとは頸椎捻挫の一つで、骨や椎間板、靭帯には損傷を伴うことがなく、検査によっても神経障害がみられないものを言います。
むち打ちと言えば、首の痛みが想像できますが、じつはむち打ちの症状は身体のいたるところに現れます?
たとえば、肩や背中、腰などにも症状は現れます。
むち打ちによる痛みの種類や出方は人によって様々です。
ズキズキと強い痛みを感じる方もいれば、首〜肩にかけて重だるさを感じたり、痺れを感じたりと多岐に渡ります。
万が一、事故にあった時に症状を抑えるためにも日頃からの首や肩周りの筋肉の柔軟性や頭を支えている筋肉の筋力UPも治療やトレーニングを通して大切ですね!
交通事故と言えば身体が痛くなるだけなく慰謝料など損害に対するやり取りも面倒だというお話を患者様からよく聞きます。
当院ではそんな煩わしことは弁護士さんに相談してもらい治療に専念できるように交通事故無料弁護士相談をサポートできるように弁護士事務所とも提携しています!
ご予約はこちら(リゼルバ)
LINE、お問い合わせはこちら
場所はこちら
あなたの思考はどっちのタイプ?
2024.07.05
堺市にお住まいの皆さん、整体に興味がある皆さんこんにちわ❗️
「身体のケアをせなあかんなあ〜」と思いつつもそのままにしてませんか?
自分の身体のことは二の次、三の次になって負担ばかり溜め込んでいませんか??
そんな自分に飽きていませんか?
変えたいと思っていませんか?
体調を壊して限界と感じた時になってようやくケアをし始めると、自分では想定していない【予想外の時間】や【予想外の通院費】を支払うことになります。
そしてそのケアが済めばまた負担を溜め込んでいく生活をしていませんか?
そして、また体調を壊して限界と感じた時になってから予想外の時間と予想外の通院費を支払ってませんか?

これは【返済方思考】(へんさいがたしこう)の人の考え方
マイナスを頑張ってゼロに戻すだけの人。
一方、【貯蓄型思考】(ちょちくがたしこう)の人の考え方はゼロにならない様に常にプラスにしていて、そのために頑張っている人のこと。
同じ「頑張り」なのになにか違うよね。。。
体調を崩した状態だと何事にも全力って出せません!
例えば、腰が痛い中、好きな人とデートしてうまくいきますか?
首が痛いまま仕事をして効率いいですか?
頭痛している中、育児をしていて子供とちゃんと向き合えていますか?
常に全力を出せるように健康をキープすることがどれだけ大事なのか分かっていてその為の行動ができている人
これが【貯蓄型思考】の人
健康をキープするために【予想内の時間】と【予想内の通院費】を支払う生活に変えてみませんか?
残念ながら健康は誰かから与えられるものではありません。
自分が自分に与えてあげることしかできません。
7/6土曜日まで毒出し整体初回割引キャンペーンをしています‼️
貯蓄型思考の人はすぐにご予約を🎵
返済型思考の人は限界を感じた時にご予約を🎵
毒出し整体の予約はこちら!
Google情報はこちら!
あなたはどっちを選びますか?
2024.07.03
身体の解毒機能の働きは万全ですか?

肝臓は人体における最大の内臓であり、代謝や解毒、ミネラルやビタミンや血液の貯蔵庫としても働く重要なところです。
日常のストレスや怒り、またはアルコール類や添加物など様々な処理に働き続けてくれる肝臓を東洋医学的にその肝臓の気を高めてくれるツボの存在があるとしたら知っておきたくないですか?
ちょっと自分自身でマッサージすることにも使えますね!
てぃだ整体整骨院で受ける事ができる毒出し整体ではこの肝臓の気を高めることができる
「大敦」(だいとん)」

写真の赤丸の場所で、足の親指の爪の外側の角にあるツボです!
肝臓にストレスがかかって働きが悪くなっていると、解毒機能が低下し血中に毒素が流れてしまうそんなことの改善に働きかけることで肝臓が元気になり働きが良くなる秘孔です。
しかも、耳鳴りや難聴にも効果ありなんです!
てぃだ整体整骨院ではここをしっかりと網羅した毒出し整体になっています。
病気に変わる前にちょっとした身体の疲れとともに内臓の働きを高めるような施術があれば便利です。
病気になってから痛みやら休養やらのリスクを背負って処方箋をもらうのと病気になる前にリスクを背負わずにケアすることができる予防線ならどちらがいいでしょうか?

処方箋は薬屋さんしか儲かりません(^^;;
予約はこちら
Google情報 てぃだ整
体整骨院
毒出し整体
2024.07.02
こんにちわ!
てぃだ整体整骨院です。
季節の移り変わりは早いものでもうすぐなつはやってきますね!
大気や気候の変化とともに体調も急激に変化します!
突然の体調不良の予防や健康維持のために我々は「毒出し」という整体法に
辿り着きました!
身体に蓄積した毒素をたいがいに排出すれば新しい新鮮な血液が全身を巡り、ホルモンバランスや自立神経の調節にもつながります。
今回は日頃から毒素を溜めない生活習慣についてお話ししたいと思います。
まず、体内に蓄積した毒素を取り除くには排泄機能を使うことです。
排泄機能として排尿に関係する腎臓、排便に関係する腸が正常に機能する事が大切です。
そのために共通して重要になるのが水分です。
1日の水分摂取量としての目安としては食事から1リットル、飲み物から1.5リットルの合計2.5リットルは理想です。
ただし、飲み物からの⒈5リットルの水は一度に飲んでも身体が吸収できません。
逆に胃に負担をかけてしまうこととなるので、1回の摂取量をコップ1杯分とし何回かに分けて摂取すると身体に負担はかかりません。
水を使ったデトックス法は飲むだけではありません。
お風呂でのシャワーも活用出来ます。
老廃物を集める機関としてリンパ節を刺激し、リンパの流れをよくすることも老廃物を排除する働きになります。
まずは温かいシャワーを鎖骨付近にあて、続いて足のつま先から膝、太もも、股関節へ向かってシャワーを当てます。
次に手の指先から手首、肘、脇の下にゆっくりシャワーを当て、最後にお臍を中心に時計まわりにシャワーを当ててお腹を刺激します。
その他にもお風呂でできるデトックス法として38度から40度のお湯で半身浴をすることもおすすめです。
新陳代謝が上がり発汗により老廃物を排出することができます。
この様に内臓の働きやリンパの流れをよくすることが毒素を溜めない生活習慣として大事です。

これらの作用として自律神経の影響を受けやすいので自律神経を調節できる鍼灸治療や東洋医学が毒素が溜まりにくい体質作りには必要です。
当院の「毒出し整体」は東洋医学で太古から使われている吸い玉と浮腫やむくみとして毒素蓄積が現れやすい足部の足底マッサージを併用したどんどん毒素を排出するための施術です。

最近いくら寝ても眠たい、やる気が全く出ないという方!
毒素に身体を蝕まれている可能性がありますね。
ぜひ毒出し整体をご体験なさってください!
毒出し整体はこちら!
〒592-8349 大阪府堺市西区諏訪森東2丁109諏訪森店舗A号 てぃだ整体整骨院
場所はこちら!
近所の整骨院で交通事故の治療が無料受けられる
2024.06.23
交通事故にあったら整骨院で治療が受けられる。
交通事故にあってしまったら?
例)車と車での事故(車に乗っていてぶつかった)
①交差点での接触事故
②後ろから追突された
③横からぶつかられた
④家族や友達の車に乗っていて事故にあった。
例)自転車と車の事故
①自転車に乗っていてぶつかられた。(すれ違いざまに接触した、車がバックしてきてぶつかられた。
②自転車乗っている時、相手の車が原因でこけた。

などがありますね。
気が動転してあわてます、まず動けない立ち上げれないは重症です。激しい痛み、見てわかるほどの外傷があれば動けません
周りの人に助けてもらいましょう、助けをお願いしましょう。携帯が使える状態なら119番に連絡しましょう。
動ける状態、多少どこかしらに痛みはあるが意識ははっきりしているならまずは警察に連絡しましょう。事故の相手側がいても話すと相手方の事を悪く思ったり自分を正当化する会話をしてしまいガチで相手もそう思っている場合もあり、ちょっとした相手との言葉のふしぶしに感情的になってしまうかもしれません。警察がくるまで冷静になりましょう。警察がきたら実況見分、聞き取り捜査に協力しましょう。事故相手との連絡先などの情報交換をしましょう。示談はしてはいけません。過失割合は警察が決めるものではありませんが、事故現場の状況については、警察が実況見分調書としてまとめたものが過失割合を決めるカギになります。
事故にあった場合はケガの程度に関わらず病院に行って診てもらいましょう、事故当初は気が張っていて身体の痛みを感じない時もありますし、後から痛くなってくる場合もあります。医師に診てもらい交通事故のことを話し痛みのある場所や身体の状態のこと伝えましょう。医師から診断書を書いてもらいましょう。
近くの整骨院で治療が受けられる。
最初に診てもらった病院が、自宅や職場から離れている場合は痛みのある場所を治療してもらうために通うのが大変な場合が考えられます。その場合は近くの整骨院、通いやすい整骨院で治療がうけられます。ムチウチ、腰痛、背部の痛み、打撲、捻挫、挫傷などです。

治療代はかからない
自分の加入している保険会社に事故の連絡を事故にあった日にできれば連絡する。医師の診断書をもとに自分が通いたい整骨院、病院を伝える。保険会社からも自分が通いたい整骨院や病院に連絡がはいり初回から無料で治療がうけられる。医師の診断書は補償を受けるにあたって保険会社、治療を受ける場所で必要になってくる。
保険会社さんには自賠責保険で利用する形にしてもらってください。
交通事故の被害者の精神的損害(こころの負担や苦痛)を金銭によって癒す賠償のことを慰謝料と言い1日4300円、最大120万支払われます。(治療費、休業補償、文章料含む)
当院は交通事故の無料弁護士相談をサポートできるように弁護士事務所とも提携しています。

交通事故といえば身体が負傷し治療を受けにいくだけでなく、慰謝料などの損害に対するやり取りを保険会社としなくては
ならなくなります。必ずしも保険会社さんがあなたの事を心配していろいろ便宜を図ってくれるとは限りません。交通事故にあっていろいろな不安や心配事があり聞きたい事やわからないことがあるのなら弁護士に相談しましょう。保険会社さんとのやり取りに時間をかけたくないのなら、弁護士さんに相談してもらい治療に専念することもできます。
このサービスは非常に高評価いただけています。