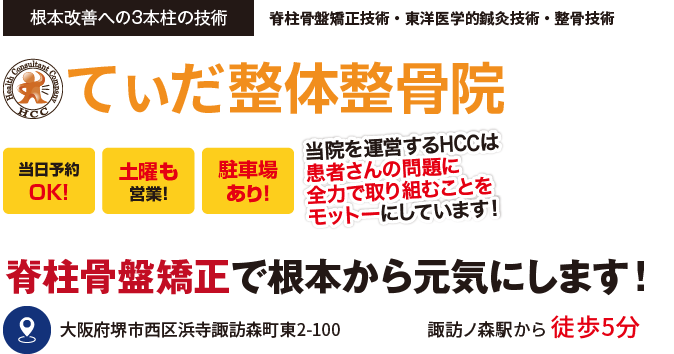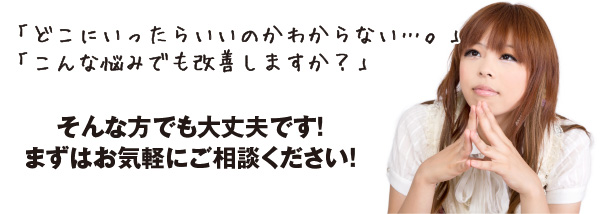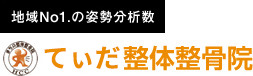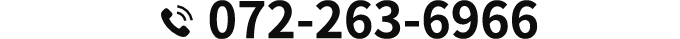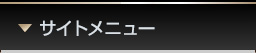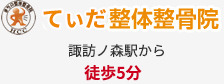脊柱管狭窄症について
2020.04.15
こんにちは!
最近、腰の痛みで来院される方が多い中、患者様からよく聞く言葉に「脊柱管狭窄症じゃないか?」「昔に脊柱管狭窄症って言われた」などがあります。
脊柱管狭窄症ってなに?
まず、脊柱管ってなに?という方も多くおられると思います。脊柱管とは、背骨、椎間板、関節、黄色靭帯などで囲まれた脊髄神経が通るトンネルです。そのトンネルが、狭くなることで神経を圧迫し、脊柱管狭窄症となります。
では、実際に脊柱管狭窄症とは?というところですが、最も特徴的な症状として、間欠性跛行(かんけつせいはこう)と言われる歩き方があります。長い距離を続けて歩くことが出来ず、歩行と休息を繰り返して歩くことを言います。歩いていると腰や足がしんどくて歩けなくなり、いったん止まって休むと回復して歩き出すことが出来るようになります。これを間欠性跛行と言います。
また、立っている姿勢や背筋を伸ばすような動き、腰を反らせる動きをすると症状が悪化することがあります。これは、体を反らすことで脊柱管が圧迫をうけ、神経の流れが悪くなることにより症状が憎悪されます。逆に、前かがみになることで、脊柱管が広くなるので症状が改善したりします。歩く時の姿勢は体を伸ばしているために脊柱管が狭くなり、休息時は前かがみになることで脊柱管が広くなります。これの繰り返しが間欠性跛行となるのです。
なぜ脊柱管狭窄症になるの?
加齢による骨や靭帯の変性が原因となることが多くありますが、労働での負担や姿勢の悪さなどで背骨や椎間板、靭帯に負担をかけることでも変性が起きやすくなってしまいます。その負担を軽減するためには、負担のかかりにくい姿勢とそれを支える筋力アップが重要になります。繰り返し負担がかかる場合や長時間同じストレスがかかる場合でも、関節や靭帯が肥厚し、脊柱管が狭くなり圧迫を受けてしまうことになります。
治療法は?
立っていられない事や、歩けないなどの日常生活に支障が出るなどの症状がきつい場合は手術が適応になることもありますが、先ほど挙げたように、運動療法としてストレッチやトレーニングでも改善することができます。その場合、どこがどのように負担がかかっているかをすることが重要になります。また、どの筋力が弱くなってしまっているかを知ることも重要なポイントになりますので、日常生活での動作や姿勢などを意識して見ていくことも大切です。
関節や筋肉が硬くなってしまうと、より負担がかかってしまうので、その負担を軽減できる身体を作ることが根本的な治療に繋がっていきますので、身体の深部へのアプローチを行っていきます。
主に鍼灸治療が適応することが多いです。吸い玉で身体のどの部分が流れが悪くなっているのかを知り、そこへ集中的にアプローチすることで、より効率的に治療を進めることができます。当院では、吸い玉はもちろん、鍼やお灸を使って直接筋肉や関節付近の組織を刺激し、緊張を緩和したり、血行や神経の流れを改善することで、症状の改善を目指します。
ストレッチとトレーニングについて
2020.02.29
当院には、痛みを抱える方が多く、施術で痛みが改善することも多くあります。しかし、「マイナスからゼロ」ではなく、来院した時よりもいい状態である「マイナスからプラス」にしていくことが重要となってきます。
それに必要となるのが、ストレッチとトレーニングとなります。痛みがましになったらそれでいいというわけではありません。痛みが出にくい身体づくり、より強い身体を作っていくためにも必要になります。
トレーニングに必要なこと
どの部分をどのように鍛えたらいいのか?
まずは、痛みを引き起こしている筋肉を特定していく必要があります。痛みにより使わなくなり、弱ってしまうことで、より痛みを引きずったりすることがあります。
その筋肉の傷が癒えても、弱いままだと、再びケガをすることに繋がってしまいます。繰り返さないためにも、姿勢の歪みへのアプローチとトレーニングやストレッチが必要になってきます。
痛めてしまっている筋肉、弱っている筋肉を鍛えることに必要なことは、その筋肉がどのような動きを起こしている筋肉なのか?を知ることが大切です。当院では、専門家によるトレーニングやストレッチのアドバイスを行っています。細かい事にはなりますが、痛みを改善、「来た時よりも元気に」なっていく為にも治療の中でトレーニングを行っていきます。
栄養に関しても、トレーニングには重要なことです。身体は、口から入るもので全て出来ています。せっかくトレーニングをしても、栄養の取り方を間違えると、効果が出ないという結果に繋がってしまうこともあります。
筋肉に必要な栄養素として、たんぱく質、アミノ酸、ビタミン、ミネラルなどがあげられます。それを効率的に補給できるのがプロテインになります。「えっ?」と思われる方も多くおられます。筋肉がムキムキの人が飲んでいるイメージのあるものですが、痛みを改善するトレーニングでもより効果の高い結果を得たいならば、プロテインを使いながらトレーニングすることをお勧めします。
普段食べている食事が「生きるための栄養」だとするなら、プロテインは「治すための栄養」といえます。
普段の食事のままでトレーニングをしても、より強くなるためには足りないことが多いです。また、筋肉を鍛えることに特化した栄養を備え、体に吸収するスピードも速くすることを考えられたものなので、とても鍛えることにとっては、強い味方となります。
ストレッチについて
固まった筋肉を柔らかくする為に必要なものになります。トレーニングと同様に間違った仕方で行うと、効果が出ないだけでなく、逆に痛めてしまうこともあります。
効果を高める為に必要なことは、ストレッチの方向と強さです。一番筋肉が伸ばされる方向に、気持ちのいい強さで行うことが重要です。ストレッチも軽く考えられがちですが、重要なポイントになりますので、正しい方法は当院でアドバイスさせていただきます!
背中の筋肉について
2020.02.29
肩の痛みと一言で言っても、いろんな原因が存在します。例えば、首が原因で肩に痛みが出たり、腰が原因で肩に痛みが出たりします。しかし、その中でも訴える方が多いのが、肩甲骨からくる痛みです。
肩甲骨の周りには多くの筋肉がついており、腕の動きや首の動きにとても重要な働きを担っています。
首に関係する筋肉とは?
首から肩甲骨についている筋肉とは、多くは上を向くときに働く筋肉です。しかし、下をずっと向いていると、頭の重みを支える為にずっと緊張していることにもなりますので、前後の動きに関わるといってもいいかもしれません。
首と肩甲骨に関わる筋肉をご紹介します。
〇頭板状筋・・・頚部の伸展、側屈、回旋
〇肩甲挙筋・・・肩をすくめる
〇僧帽筋・・・肩をすくめる、肩甲骨を内側によせる
腕に関係する筋肉とは?
腕を動かすときにも肩甲骨は関係しています。特に重要なのは、「肩甲上腕リズム」といい、簡単にいうと、腕が上がると肩甲骨も一緒に動いていくというものです。正常ならば2:1のリズムと言われているのですが、このリズムが崩れると、肩や腕の痛みに繋がる原因ともなります。
〇三角筋・・・腕を前・外側・後ろにあげる
〇烏口腕筋・・・腕を前にあげて反対の肩を触る動き
〇広背筋・・・腕を後ろにまわす
〇大円筋・・・腕を後ろにまわす
〇棘上筋・・・腕を外側にあげる
〇棘下筋・・・腕を後ろにまわす
〇小円筋・・・腕を後ろにまわす
〇肩甲下筋・・・腕を前にまわす
〇上腕二頭筋・・・肘を曲げる
〇上腕三頭筋・・・肘を伸ばす
以上が、腕と肩甲骨を繋いでいる筋肉となります。
首や腕から肩甲骨への筋肉を傷めたり、硬くなったり、弱くなったりすると、肩の痛みに繋がることが多いのです。
肩の痛みがあり、その痛い部分だけを治療するのではなく、首や腕を治療することも大切になってきます。「木を見て森を見ず」ではありませんが、根本治療を目指す我々は、とても辛く感じている症状を改善するために、それに関わるすべての筋肉をチェックする必要があります。
腕や首の筋肉のセルフケア
肩の痛みを改善するためのストレッチやトレーニングをご自分でも行うことで、より早い改善が期待できます。施術などにより改善してきた状態を維持、改善に繋げていく為に重要な要素となります。
また、上記に挙げた筋肉については、大きな動作を行うアウターマッスルという外側の筋肉ではなく、インナーマッスルという深部の筋肉が多くあります。その筋肉をストレッチ、トレーニングすることで肩の痛みを軽減することに繋がっていきます。
基本的なこととして言えるのは、「重い負荷」ではなく、「軽い負荷」でトレーニングを行うことです。
動きはじめや、位置を維持する筋肉として使われるものなので、インナーマッスルへのアプローチを行うことで肩の改善を見込めます。
そのために、当院では電気治療や運動療法を始まりとして、鍼灸治療で深部へのアプローチを行っています。
肩の痛みに関係する関節について
2020.02.15
一言で肩といっても腕と体の関節だけでなく、それ以外にも沢山の関節があります。
肩に関与する関節
①第一肩関節
皆さんがご存知の関節で、肩甲骨と上腕骨からなる関節。
②第二肩関節
肩甲骨と上腕骨、さらに鎖骨からなる関節。
③肩甲胸郭関節
肩甲骨と肋骨からなる関節。
④肩鎖関節
肩甲骨と鎖骨からなる関節。
⑤胸鎖関節
胸骨と鎖骨からなる関節。
上記5つの関節からなっています。
関節はどう作られているの?
骨と骨が繋がっている部分と考えられる方も多いと思います。しかし、骨と骨との繋がりには2種類あり、「不動結合」と「関節」になります。
「不動結合」とは、頭蓋骨や恥骨のように、軟骨や膠原線維などで直接連結しているもので、連結している骨同士は動きません。
「関節」とは、一般的に言われる関節で、骨と骨との間にわずかな隙間があり、これを関節包といわれる膜状のものが包んでいます。その隙間には少量の滑液によって満たされているので、骨同士の連結は滑らかに動かす事ができます。
つまり、骨と骨が直接繋がっているものと、そうでないものがあり、動きによって痛みが出るものは、後者の「関節」という事になります。
関節には軟骨成分があり、骨と骨との接触面に存在しています。クッションの役割や円滑さを保つためにも必要なものです。
また、骨と骨とを連結させる靭帯があり、行きすぎないように止めるベルトの役割もしてくれています。
場所によって関節の動き方が違い、種類も多くあります。
蝶番関節(膝、肘、指)・・・一方向にしか動きません。
鞍関節(親指)・・・人が馬の鞍にまたがった形。
球関節(肩関節や股関節)・・・受け皿と球状の骨が組み合わさった形。
楕円関節(手首)・・・前後左右に動かす事が出来ますが、回旋は制限される。
半関節(恥骨結合など)・・・ほとんど動かない関節。
平面関節(足根部、手根部)・・・関節を作る時は平面。スライドするように動くが、範囲は狭い。
車軸関節(首や肘)・・・一方に突起、一方に差し込まれる形でできている関節。
どうして傷むのか?
そもそも、多くの関節はなぜ傷んでしまうのか?
関節を動かしているのは筋肉です。筋肉が腱となり、骨について動かすのですが、その筋肉の動きに問題があると、関節の動きが悪くなります。
その動きの悪さに気づかない方が多く、いつも通り動かす事により筋肉に無理が働き、筋肉や関節を直接傷つけてしまうのです。
それが繰り返したり、長時間に及ぶと、負担や傷がひどくなり、痛みとなって現れるのです!
肩の痛みと肩甲骨の関係について
2020.02.15
肩甲骨の動きってご存知ですか?
「肩が痛くて、肩を動かしてるんですけどね~」と言われる方、とても多いです。しかし、動かし方を見ていると、肩甲骨が動いていないではないですか!!
肩甲骨は、肩の関節のように大きく動く関節ではありませんが、大きく6つの動きをしています。
①挙上・・・肩をすくめる動き。デスクワークや重い荷物を持つと使われます。
②下制・・・肩をすくめる動きから肩を下げる動き。
③外転・・・腕を前ならえの姿勢からさらに腕を前に伸ばす動き。肩甲骨同士が離れる動きです。
④内転・・・胸を張る姿勢で、肩甲骨同士が近づく動きです。
⑤上方回旋・・・高い所の物を取る時の動き。腕を上に上げると動きます。
⑥下方回旋・・・腕を上に上げた姿勢から元に戻す動きです。
肩甲骨は、上記の6つの動きを行なっています。
それに伴って使われる筋肉が、疲れたり、筋力が弱かったり、筋肉を傷めたりすると、腕が動きにくくなったり、痛みを伴う事になります。
肩甲骨と上腕骨の関係
腕を上げるという事は、肩甲骨も動くという事になります。肩甲骨と上腕骨の関係は、「肩甲上腕リズム」という、お互いのバランスを取って成り立っています。
腕を横に上げた時(外転)、肩甲骨も上方回旋が始まります。上腕骨が2度上がれば、肩甲骨は1度上がるという、「2:1」のリズムで動いています。
その肩甲上腕リズムが何らかの原因で崩れてしまうと、周りの筋肉のバランスが崩れ、動きが悪くなったり、痛みを伴ったりします。
肩の治療には、このリズムを正常に戻していく事が大切になってきます。
肩甲骨の動きに関与する筋肉
肩甲骨の6つの動きに関与する筋肉、すなわち肩の痛みに関わる筋肉は下記のものがあります。
挙上・・・肩甲挙筋、僧帽筋上・下、大・小菱形筋
下制・・・僧帽筋下、小胸筋
外転・・・前鋸筋、小胸筋、僧帽筋上
内転・・・僧帽筋中、大・小菱形筋
上方回旋・・・前鋸筋下、僧帽筋上
下方回旋・・・大・小菱形筋、僧帽筋下、小胸筋
この筋肉が、どこでどのような動きで固くなったり、傷めてしまっているのか?
それを分析して治療にあたる事で、肩の痛みの改善はより早くなります。
また、冒頭に述べた「肩を動かしてるんですけどね」についてですが、肩甲骨ではなく、上腕骨のみを動かしている方が多く、肩甲骨を動かす事が出来ず、肩の痛みから解放されにくいという事があるのです。
上記に述べた肩甲骨の動きを意識して、肩を動かす事で、トレーニングやストレッチなどの効果も変わっていきます。
動かしているのになかなか変わらないという方は、ぜひ肩の動かし方を見直してみて下さい!
腰痛のトレーニングについて
2020.01.18
この季節は、腰に痛みを訴える方が増えてきます。ギックリ腰などもこの季節に多いです。その腰の痛みは繰り返し出ている方が多いのも事実・・・なぜ繰り返すのでしょうか?
なぜこの寒い季節に腰を傷める事が多いのか?
暖かい季節にも腰を傷める方はおられますが、寒い季節になるとより一段と腰を傷める事が多くなります。
それは、寒さで筋肉が緊張する事、血管が収縮し血行不良を起こしやすい事、冷えで神経の流れが悪くなり身体の動きが悪くなる事が挙げられます。
しかし、この季節に腰を傷める方は、他の季節にも傷めている事が多いです。来られる患者様も、「前から腰は悪いんやけど・・・」という言葉をよく耳にします。
寒い季節だけでなく繰り返すのはなぜ?
以前から腰に負担がかかっている事が多く、寒い季節はより身体の状態が悪くなる為、ギックリ腰など急な痛みを発症しやすいと言う事がいえます。腰に負担がかかっているとは、座りっぱなし・立ちっぱなしなどの長時間の不良姿勢、腰に負担がかかる姿勢や動作を繰り返す、腰が反り返っている・または前かがみになっている。などが挙げられます。
当院では、腰を傷める原因となる姿勢を分析する事から治療を始めていきます。その分析をする中で多いのが、反り返っている姿勢です。
原因としては、お腹の筋肉が弱っている事で背骨が彎曲してくる事です。それにより、荷物を持ったり、動いたりしなくても、腰に負担をかけてしまう事が多いのです。
痛みを繰り返さない身体を作る事で大切なのは、ストレッチやトレーニングを行う事です。
どんなトレーニングがいい?
上記に挙げた不良姿勢や繰り返す負担に耐えられる身体を作るには、身体を支える筋力を上げる事が一番大切です。また、ぎっくり腰などで傷めた後にトレーニングを行う事で、再発を予防することにも繋がります。
お腹の筋力が低下する事で、背骨の前方への彎曲を止められず、身体が反り返ってしまう事が、腰を傷めやすい姿勢を作る原因になっている事が多いです。では、どのようにお腹の筋力を鍛えたらいいのでしょうか?
みなさんが知っている腹筋とは、
①仰向けで寝ころぶ(足を伸ばした状態や膝を曲げた状態)
②足が浮かない様に押さえる(タンスなどにつま先をひっかける)
③上半身を起こす
これではないでしょうか?
そもそも、腰が痛い方にこの動きは難しいです。また、負担も大きい為に、より傷めてしまう方もおられます。また、お腹に力を入れる事が出来ない方は、首の力を使って起き上がる為に肩や首を傷めてしまう方もちらほら・・・
まずは、インナーマッスルを鍛えて、背骨を支える筋力をアップさせる事が重要です!
まずはドローイン!!
①仰向けで寝ころぶ(頭の下に枕を入れたり、足を曲げたりしない)
②腰の下に手や薄いクッションを入れる(身体が反らない程度)
③腰の下の手やクッションを腰でつぶすように力を入れる(息を吐きながら行う)
④5秒間力を入れ続け、3秒で力を抜く
⑤③~④を繰り返す
上記の方法がドローインといって、腹式呼吸を応用した腹筋になります。上半身を起こしたりする事がないので、腰に新たな負担をかけるなく、鍛える事ができます。
やり方を間違えると、効果が減少したり、新たな負担で違う場所を傷めたりすることもあります。
当院では、筋肉と関節の専門家からのアドバイスを受けて、トレーニングやストレッチを行う事が出来ます。自宅で行う事も大切ですが、出来ない事は院で行ってもらい、根本から治療していく事が大切です!
肩のトレーニングについて
2020.01.15
今回は、肩のトレーニングについて解説させていただきます。
肩の痛みの原因として、五十肩、腱板損傷、滑液包炎など、肩の痛みの原因も多岐にわたります。痛みがあると、自然にかばい、使わなくなります。痛みが無くなったとしても、痛みが出る以前と同じように使えるようになるには、筋肉トレーニングが必須となります。使わなくなった筋肉が弱ったままいつも通り使うと、違う筋肉に無理が生じ、違う筋肉を傷める原因となってしまいます。
どんなトレーニングがいいの?
一言に肩のトレーニングといっても、方法もたくさんあります。どこが痛いのか、どういう動きで痛みが出るのかを分析し、どの筋肉が弱っているかを見極める事が大切です。
また、トレーニングをする道具もたくさんあります。ダンベル、ゴムチューブなど負荷をかけるものや、自身の腕の重みでトレーニングする事も出来ます。
今回は、初期の段階で行う、ゴムチューブを使ったトレーニングをご紹介します。今回のブログを参考にして頂き、トレーニングをする事で根本治療に繋げていただければと思います。
どこを鍛えるのか?
どの様な動きで痛みがでるのかによって変わりますが、今回は腱板損傷や五十肩で弱りやすい筋肉、「腱板」のトレーニングについて解説させていただきます。
腱板とは、肩の深い部分の筋肉で、インナーマッスルともいいます。身体と腕を繋げている筋肉で、腕をぶらさげているだけでも負担がかかる筋肉です。しかし、鍛えるということは、いつも以上に負荷をかけないといけないので、ぶら下げている負担だけでは鍛える事は難しいです。
しかし、ダンベルなどを使って大きく肩を動かすと、インナーマッスルではなく、大きな表面の筋肉のアウターマッスルを鍛えることになるので、効率が悪くなってしまいます。インナーマッスルを鍛える事で大切なのは、「軽い負荷」で「小さな動き」で「回数を多く」行う事です。
それはなぜか?
インナーマッスルが一番働く時は、関節が動きだす最初だからです。肩を上げ始める最初の動きに一番使われるので、上げ始める最初の動きに負荷をかけて、それ以上は動かさない。それが、インナーマッスルを鍛える極意だと言えます。
トレーニング方法は?
ゴムチューブを使う事で、軽い負荷をかけながら、小さな動きを再現する事ができるので、インナーマッスルのトレーニングには、ゴムチューブが最適だと言えます。ダンベルなどでも行う事は出来ますが、動きの制限などの注意点が多い為に少しご自身で行うには難しいです。また、軽いダンベルでも500グラムはあるので、負荷としては少し重くなってしまう事があります。ですので、ゴムチューブでのトレーニングをお勧めします。