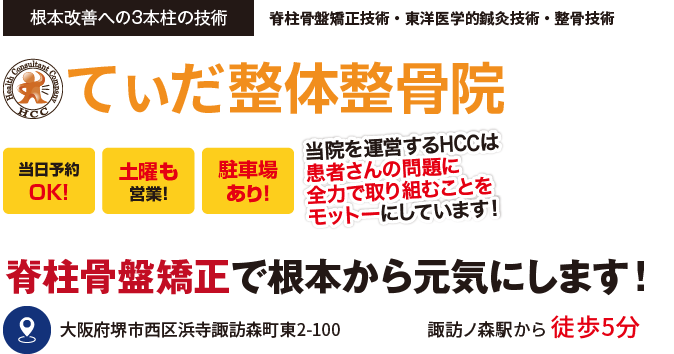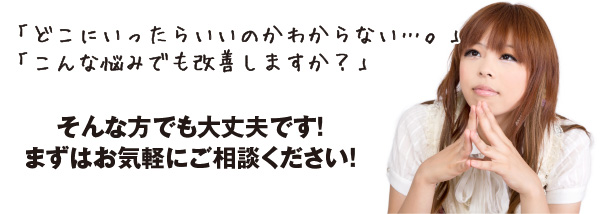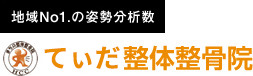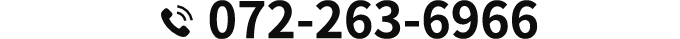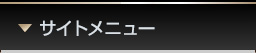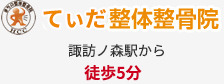膝のトレーニングについて
2020.01.15
膝の痛みにお悩みの方多いと思います。変形性膝関節症、半月板損傷、靱帯損傷など、膝に痛みが出る原因は多岐にわたります。
しかし、それら全てに言える事は、痛みで膝をかばうことで、痛みが出ている足を使わなくなります。これは、意図してだけではなく、無意識下で行われるでもあるので、全てに当てはまります。使わなくなると、筋肉が弱くなり、体重を支える事が困難になっていきます。骨格を支えているのは筋肉です。その筋肉が弱くなると、直接関節に負担がかかるようになるので、より痛みがきつくなったり、治りが遅くなると言う事が起きてしまいます。
根本的に痛みを治療していく為には、筋肉トレーニングが必須となっていきます。
どこを鍛えたらいいの?
一言に膝のトレーニングといっても、どこをどういう風に鍛えたらいいのでしょうか?症状や、傷めている場所によって変わっていきますが、今回は、膝の痛みの原因として特に多い「変形性膝関節症」のトレーニングについて解説を行っていきます。
変形性膝関節症は、膝の内側の軟骨がすり減り、太ももとふくらはぎの内側の骨がとがるように変形し、直接当たる事で痛みが出てしまいます。また、股関節が外側に広がり、膝から下は内側に入ってしまう事で、О脚になってしまう事が多くあります。О脚になると、足の内側の筋肉は使われなくなることで衰え、逆に外側の筋肉を良く使う様になるので、外側の筋肉は緊張して硬くなります。内側で支える事が出来なくなり、膝の内側に痛みが出てしまいます。
そこで、鍛える筋肉は、「内側広筋」(ないそくこうきん)と言われる太ももの内側の筋肉になります。
内側広筋とは?
太ももの前面にある大きな筋肉を「大腿四頭筋」(だいたいしとうきん)と言います。骨盤の前から膝の下まで走っている筋肉で、膝のお皿を巻き込んで膝の下につきます。股関節と膝関節の2つの関節の動きに関与する「大腿直筋」、膝関節の動きに関与する内側の「内側広筋」、外側の「外側広筋」、真ん中の「中間広筋」の4つから成り立っています。
その内側の筋肉を鍛える事で、変形性膝関節症からくる痛みを軽減する事ができます。
大腿四頭筋の働きは、主に膝を伸ばす動き、膝関節の伸展になります。ですので、膝を伸ばす動きで鍛える事が出来ます。
しかし、4つの筋肉が動いて膝を伸ばすので、内側だけ効率よく鍛える事が必要になります。
肩の痛みについて
2019.11.12
肩の痛みと一言で言っても、沢山の症状があり、その人によって痛む場所も変わってきます。特に、肩には沢山の関節があります。
よく痛む関節
①肩甲上腕関節
いわゆる肩関節。肩甲骨と上腕骨からなら関節で、人体の中でも最も多方向に幅広く動く関節でもあります。骨と骨のつなぎ目に、関節包という袋と腱板(けんばん)という筋肉があり、その関節包や筋肉の痛みが大きな部分を占めます。
②肩鎖関節
肩甲骨の屋根にあたる肩峰(けんぽう)と鎖骨の先端とからなる関節で、肩の痛みで見落としがちになる部分でもあります。肩甲上腕関節よりも動きは少ないですが、肩の動きで支点になる部分なので、動きが少ない分力の逃げ場がないので、負担がかかりやすい場所の一つと言えます。
③肩峰下滑液包炎
肩峰と腱板の間にあるスペースであり、クッションのような役割りをしています。腱板の炎症がある場合は、少なからず滑液包にも炎症がある事が多く、肩の注射などはこの部分にする事が多いです。
傷みやすい部分としてこのような部位がありますが、もっとたくさんの関節があります。複雑で多様な部位なので、たくさんの関節の中から、どこが傷んでいるかを特定する事が重要になります。痛みが出る事が多いといわれています。
傷む場所は?
肩関節の周囲の痛みとしては、肩甲上腕関節が原因の事があり、関節包と腱板がキーポイントとなります。関節包が炎症を起こす事で「五十肩」「凍結肩」などといわれることが多いです。さらに、肩の前側に痛みがある場合は、上腕二頭筋長頭腱炎が疑われます。上腕二頭筋というのは力こぶの筋肉ですが、長頭と呼ばれる筋肉の腱が関節の中に入り込むようになっていて、そこでの炎症がおこりやすいと考えられています。
また、肩関節は幅広く多く動く関節なので、不安定になりやすいということがあります。その為、脱臼や不安定な状態で肩を使っている為に痛みが出ているい事が多くあります。
肩の上の痛みとは、肩鎖関節の痛みを示している事が多いです。関節の動きが少ない部分でもあるので、大きな動きでの負担がかかりやすい部分でもあるので、注意が必要です。脱臼や骨折なども起こりやすい部分ですので、肩の動きとして水平内転という動きにより負担がかかります。水平内転とは、腕を胸の前を通して逆側の肩を触るような動きになります。肩鎖関節の圧力が高まると考えられており、その動きにより痛みが誘発される事が多くあります。
年齢の変化も大きなポイントです。どうしても身体というのは経年変化起こしていきます。特に肩関節は大きく動く関節なので、広い可動域の代わりに安定性を失っている関節ともいえます。関節周囲の組織に問題が起こりやすくなっていきます。関節包や腱板というインナーマッスルが障害を受けやすいということになります。
40~50歳代
年齢的に耐久性が衰えてきたなかで、肩の関節はまだまだ使う・・そんなご年齢なのではないかと考えます。靭帯や関節包が固まり始めているなかで、ストレッチや運動が大事な時です。
60歳以上
より肩の耐久性が落ちてきているので、五十肩などより多くなってくるのが「腱板損傷」です。動きが悪く、痛みを伴うので五十肩と思って来られる方も多いのですが、精密に検査をすると腱板を損傷していると言う事が多いです。
重労働やスポーツでのオーバーユース、使い過ぎによる肩の痛みも多くあります。動かす時の姿勢や動かし方でも肩に掛かる負担は変わりますので、お気軽にご相談ください。
冬に向けての準備
2019.10.30
気温もグッと下がり、衣替えをしたりと、設備や施設の準備だけではなく、体と心の準備もしてみませんか?
身体のために日照時間が大切
日本だけでなく、アメリカやヨーロッパなどでも、冬の日照時間は劇的に減少します。会社に出る頃には外は暗く寒くなっている事が多いです。日の出のように徐々に明るくなって目覚め、暗くなる事で眠りにつく事が質の良い睡眠を取る事にも重要なポイントです。また、身体に自然光を浴びる事でビタミンが体内に生成されたりと、身体にとってはとても重要になってきますので、寒くなるからといって室内にこもったりせず、外に出る事が大切です。概日リズムという体内のリズムも乱れがちになりやすいので、積極的に外に出ていきましょう!
水分補給も需要です
冬の大気は、乾燥しています。暑い夏は汗もかくため大量に水分補給する方も多いですが、冬は水分補給が極端に減る方も多くおられます。しかし、大気が乾燥している冬もしっかりとした水分補給が必要となります。脱水症状となり、喉や鼻、お肌も乾燥して風邪をひきやすくなったり、痒みや湿疹などにもつながってしまいます。意識的に水分補給する事が大切です。また、空気中の乾燥を防ぐ加湿器も重要なポイントとなってきます。水分補給をするだけで、病気を防ぐ事ができると言われる程、冬の水分補給は欠かせないものとなっています。
冬場に注意すべき事
冬の運動は、血流を良くし、暖まる効果もあるのでとてもオススメです。しかし、室内と屋外の温度差により、血管が収縮し、交感神経も緊張してきます。すると、血圧も上昇し、心筋梗塞や脳卒中、ごく稀に動脈瘤の破裂などを招く危険性があります。また、筋肉も硬い状態となり、伸縮性が悪い状態になります。そのままの状態で運動を始めると、ケガに繋がる可能性も大きくなります。
その危険性を低下させる為に注意すべき事は3つあります。1つ目は、極端な温度差をなくす事です。防寒はもちろんですが、外に出る前に部屋のエアコンを切って、寒さに慣れてから外に出る事も必要です。2つ目はウォーミングアップ。手足をほぐすなどの軽い運動を行い、反動をつけないストレッチでゆっくり身体を伸ばす。硬い筋肉をほぐす効果があります。ほぐれてきたらラジオ体操などの動くストレッチをするとより効果的です!
冬になると、病気やケガが多くなるのはこのような事があるからなのです。
暖かい季節から冷える季節。『冷えは万病のもと』と言われるように、すべて縮んでしまい循環も悪化してきます。体も心も、冬が訪れる準備をし、元気な毎日を過ごしていきましょう!
〇〇の秋
2019.10.30
段々と気温も下がり、季節の変わり目となってきました。
秋になると、『〇〇の秋』という事がよく言われます。
食欲の秋
読書の秋
スポーツの秋
人が集中しやすい気温が18度前後だという事で、読書の秋や芸術の秋などと言われています。
食欲の秋は、実りの季節や冬眠の前に蓄えておく本能的なところから、そう言われているとあります。
スポーツの秋は、東京オリンピックをきっかけとして、10月10日の体育の日もあり、そう言われるようになりました。
体の変化から、そう言われる事が多くなるということもあり、秋は体調の変化を感じる方も多くなる季節です。
昼夜の気温差が大きい季節
気温差が大きくなると、日中と朝晩での着るものの調節が難しくなったり、日中に行動すると暑く汗をかき、そのまま日が暮れると気温が下がり体が冷えてしまう。
そういったことの繰り返しにより、体調を崩す方も増えてきます。
また、体内の調節に力を発揮する自律神経が乱れやすいという事で、体調を崩す方が多いです。
自律神経が乱れること
汗をかいたり、血管を広げたりに働く交感神経と、リラックスの神経である副交感神経のバランスが崩れると、リラックスすべき時に体が興奮状態にあり休める事が出来ない、痛みを感じる神経でもあるので、より痛みを感じやすくなる季節でもあります。
体温の調節も自律神経で行うことがあります。いつもエアコンで室温が一定に保たれた空間にいることで体温調節が下手くそになり、自律神経が上手く働かずに過ごしている方も多いのではないでしょうか?
自宅で簡単に出来る自律神経を整える事
◯生活リズムの改善
◯食事内容の改善
◯睡眠の改善
◯適度な運動
他には、ストレッチやトレーニングもこれに含まれます。筋肉の緊張が強いと血流が悪くなり、神経の流れも悪くなってしまいます。
また、不良な姿勢もその一つです。長時間同じ姿勢をとる事が多い事務作業などは、猫背になり、背中や腰、肩首の筋肉が硬くなり、血流や神経の流れが悪くなってしまいます。
てぃだ整体整骨院では、筋肉と関節の専門家からのストレッチやトレーニングのアドバイスを受ける事が出来ます!
セルフケアで大切なのは、正しい方法と継続です!
間違った方法では、身体を痛めてしまう事になりかねません。ぜひ、お気軽にご相談ください!
腰から足の痛みについて
2019.09.13
腰から足に痛みが出る。多くは「坐骨神経痛」と診断される事があります。
しかし、患者様の中でも多いのが、「坐骨神経痛」という病気だと思っている方が多いこと。
坐骨神経痛は神経痛の一つ。
腰から足にかけて伸びている坐骨神経と言われる大きな神経が、何らかの原因によって圧迫されたり、引き伸ばされたりして、神経の流れに異常をきたすことを言います。腰から足に痛みやしびれが出る症状の事をいいます。
原因とは?
坐骨神経痛と一言にいっても、原因は様々です。
年齢が若い場合は、腰部椎間板ヘルニアが多く、年齢が高くなると腰部脊柱管狭窄症が増えてきます。どちらも、神経を圧迫する事で坐骨神経痛を引き起こします。
◯腰椎椎間板ヘルニア
背骨は、椎体という骨と、椎間板というゼリー状のクッションで出来ています。強度の負荷などの何らかの理由で椎間板が押し出され、脊柱管を通っている神経を圧迫する事で痛みやしびれが起こります。
◯腰部脊柱管狭窄症
脳から背骨に沿って伸びてきた神経が通る道で、背骨の中を通っています。腰のあたりの背骨の中の通り道が何らかの理由で狭くなり、神経が圧迫される事で痛みやしびれが起こります。
これら以外で多いのが、「梨状筋症候群」です。
お尻の深い部分にある梨状筋という筋肉が縮んだり、引き伸ばされたりする事で、その間を通る坐骨神経が圧迫され、痛みやしびれを引き起こします。
症状はどんなもの?
◯身体(腰)を動かすと痛みが出る
◯安静にしていてもお尻や脚が痛んで眠れない
◯脚だけでなく腰にも痛みがある
◯身体をかがめると痛みがあり靴下がはけない
◯立っているとい、痛みがあって立ってられない
など
神経の仕組みについて
2019.09.02
体を動かすには、神経の流れが必要になります。腕を曲げようと思えば、腕を曲げる筋肉に脳から神経を伝達し、筋肉の収縮が起こり、腕が曲がります。その神経の流れが悪くなるとどうでしょうか?
神経とは?
情報の統合の為に体の正中に集合して存在する中枢神経系と、中枢外に存在し個別に線維として認識される末梢神経系に分ける事が出来ます。
シナプスという触手のような部分を介して信号が流れており、それがスムーズに流れる事が、神経の流れが良いと言う事になります。逆に悪くなっていると言う事は、身体のどこかでシナプスがおかしくなったり、それ以外の神経の連続性が断たれる事でうまく流れない事を言います。
神経の流れが悪いと?
その神経の流れが悪くなると、筋肉や関節など、意図的に動かしている部分の動きが悪くなるのは当然で、血流や脈拍なども正常ではなくなる事があります。
うまく働かない筋肉を、いつもと同じように使うとどうなるでしょうか?
例えば、10キロもてる筋力を持っている方が、神経の流れが悪くなり、5キロしか持てなくなっているとします。しかし、本人は神経の流れが悪くなっている事に気づかず、いつもと同じように10キロ持つ事をしていると、5キロの力を無理している事になります。
筋肉を無理して使うと、傷ついたり、ちぎれたりという事が必然として起こります。そのような事を繰り返し行う事で、痛みとなり、なかなか治らなくなったり、同じ症状を繰り返すと言う事に繋がります。
自宅で出来る神経の流れを良くするには?
まずは、姿勢の歪みを正す事が大切です。背骨にはいくつもの関節があり、その関節の間から神経が全身に分布していきます。その根っこの部分に負担がかかると、全身をめぐる神経の流れが悪くなってしまいます。
姿勢を正す事で、神経の流れを正常に保つ事が出来ます。ご自身の日常生活の中で、同じ姿勢を長時間取っていたり、繰り返し同じ事を行う事はないでしょうか?
良い事も悪い事も習慣になっている物に対して、一度見直してみる事で、どこにどういう負担がかかっているかを知る事が大事です。
また、神経は温かい環境で流れが速くなると言う事があります。冷え症を抱えている方等は、より神経の流れが悪くなりやすいと言えるでしょう。湯船に浸かる習慣を身につけ、身体の隅々まで神経の流れをいきわたらせる事が重要になってきます。
また、運動やストレッチを行う事で、関節や筋肉に掛かる負担を減らし、神経の流れを改善する事も出来ます。
当院では、専門家によるトレーニングやストレッチの指導も行っています。
ご自身でのセルフケアには間違いも沢山あります。方法や回数、時間等、より効果的に自宅でのケアを行うには、とても大事な事です。
セルフケアの重要性
2019.08.13
セルフケアとは、自分自身をケアする事、すなわち自分自身で世話をする・面倒を見る事です。
軽度のけがや不調の多くは、自然治癒力で治るものです。僕達は、その自然治癒力を高めるために、いろいろな手段を使って患者様へアプローチをしています。
しかし、24時間365日関わり続ける事は不可能に近いのです。日常生活の中で体に負担をかける場面があったとしても、それを制止したり注意したりする事が出来ない事が多いものです。
そこで、セルフケアが重要になってきます。
セルフケアとは?
十分な休養をとり、適切な栄養を取り、適切な運動をすれば自然治癒力が活発に働き、細胞レベルでも自分自身が体を治してくれるのです。
元気な毎日、健康な毎日を過ごす為には、栄養面、精神面、肉体面の3つが充実している事が必要です。その中で、なにがどのように足りないか、増えすぎているかを見極め、施術に当たります。
足りない部分を増やしたり、逆に増えすぎている部分を減らしたり、生活習慣の中で、ご自身でしか分からない事も多いと思います。
簡単に出来る自然治癒力アップ法
プラス思考でいる事は、前向きな気も通夜明るい気もつは治癒力を高め、マイナス思考やストレスは治癒力を下げるとよく言われています。しかし、ここに大きな落とし穴があります。それは、知識と実際のギャップです。マイナス思考の方が、いくらプラス思考になりなさいと言われていも、どうしたらいいのかが分からない為、大変困惑する事になります。変わるきっかけが多くあればあるほど、なにかしらのきっかけで回復力が促進されて行きます。無理に変えようとはせず、「今のままでいいよ。」という部分からスタートしましょう。
栄養面では、5大栄養素といわれている「無機質」「たんぱく質」「炭水化物」「脂質」「ビタミン」をバランスよく摂取する事が大切になります。また、女性ホルモンを高める事で抗酸化作用があるイソフラボン、食物繊維、乳酸菌など、身体の働きを十分に高めてくれる食物を意識的に取り入れる事で、より自然治癒力を高める事に繋がります。
肉体面でのアップ法は、ストレッチやトレーニング、ウォーキングなどが挙げられます。仕事が忙しい、そもそも運動不足で体の動きが悪いので運動をしないなども多く伺います。筋力の低下から姿勢が悪くなり、健康状態が悪化し、より衰える事で体を動かす事が難しくなり、筋力の低下に繋がっていきいます。これを、僕は負のスパイラルと呼んでいます。何かを変えない限り、流れは変わりません。簡単な運動やストレッチから始める事でも、自然治癒力を高めるきっかけになります。
根本的な背骨の矯正や骨盤矯正、身体の内部への鍼灸を使ったアプローチ、身体の専門家によるストレッチやトレーニングのアドバイスなどを駆使して、一人一人の患者様に合った治療を提供していきます。
Google検索で
堺市 西区 整骨院
上記クリックしていただけますと問い合わせや予約のお電話やてぃだ整体整骨院までの道のりがわかります!